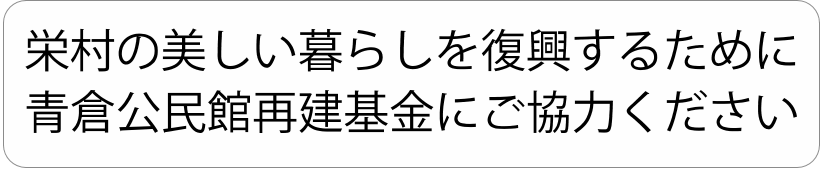- 栄村の美しいくらしを育てていく村民と大学生の協同プロジェクト
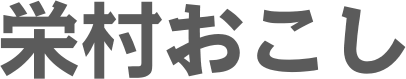
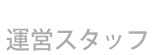

3月12日午前3時59分、震度6強の直下型地震が、長野県最北部に位置する栄村を襲った。震源は深さ8キロ、
地震の規模は推定マグニチュード6.7。半日前に起こった東日本大震災に誘発されたかのように、「その日の深夜」だった。
村内外を結ぶ道路は雪や土砂でふさがれ、孤立した小滝集落の住民は、ヘリコプターで避難所へ移送された。
地震直後の写真などはこちら

栄村は、「豪雪の村」として知られている。自然の豊かさと多彩な暮らしの営みが評価されて「にほんの里100選」にも 選ばれた美しい村。しかし、震災による雪崩や土石流で、山々が崩れ落ち、瓦礫が地面を覆い、一瞬にして様相を変えてしまった。 家屋は51棟が全半壊、JR飯山線はレールが宙吊りになり、県道の路肩50mほどが崩落。 多くの村民の暮らしを支える田んぼには亀裂が入り、水路が山ごと崩壊するなどの被害で、今年の作付けも危ぶまれている。

にもかかわらず、東日本大震災とそれに続く福島第一原発の事故の影で、栄村の被害状況は、
十分全国に伝わっているとは言い難い。東北の被災地へは既に数百億円に上る義捐金が集まっているが、
栄村への直接の義捐金は1億5千万円程度だ。警察庁緊急災害警備本部がまとめた「東日本大震災の被害状況と警察措置」では、
長野県は対象地域に含まれず、内閣官房震災ボランティア連携室のプロジェクト「助け合いジャパン」にも、
栄村の名前はなかった(4月8日現在)。いまのところ、栄村に「東日本大震災」の義捐金が配分されるかどうか、
確かな見通しはない。
村人たちにとって、今一番不安な問題は住宅だ。約2300人の村民の平均年齢は56歳。年金生活の高齢者は、家を直す資金を
借りることは難しい。家が直せたとしても、主な生業である農業が復興できなければ、どんなに村が好きでも住み続けられる保証はない。
この村が従来の生活を取り戻すには、一時的な物資ではなく、生活と産業の基盤を復興していく長期的な支援が求められている。

震災前の美しい青倉の棚田。今は雪をかぶっているが、雪解け後に、水路の点検や田の底に地割れがないかの調査が必要だ。